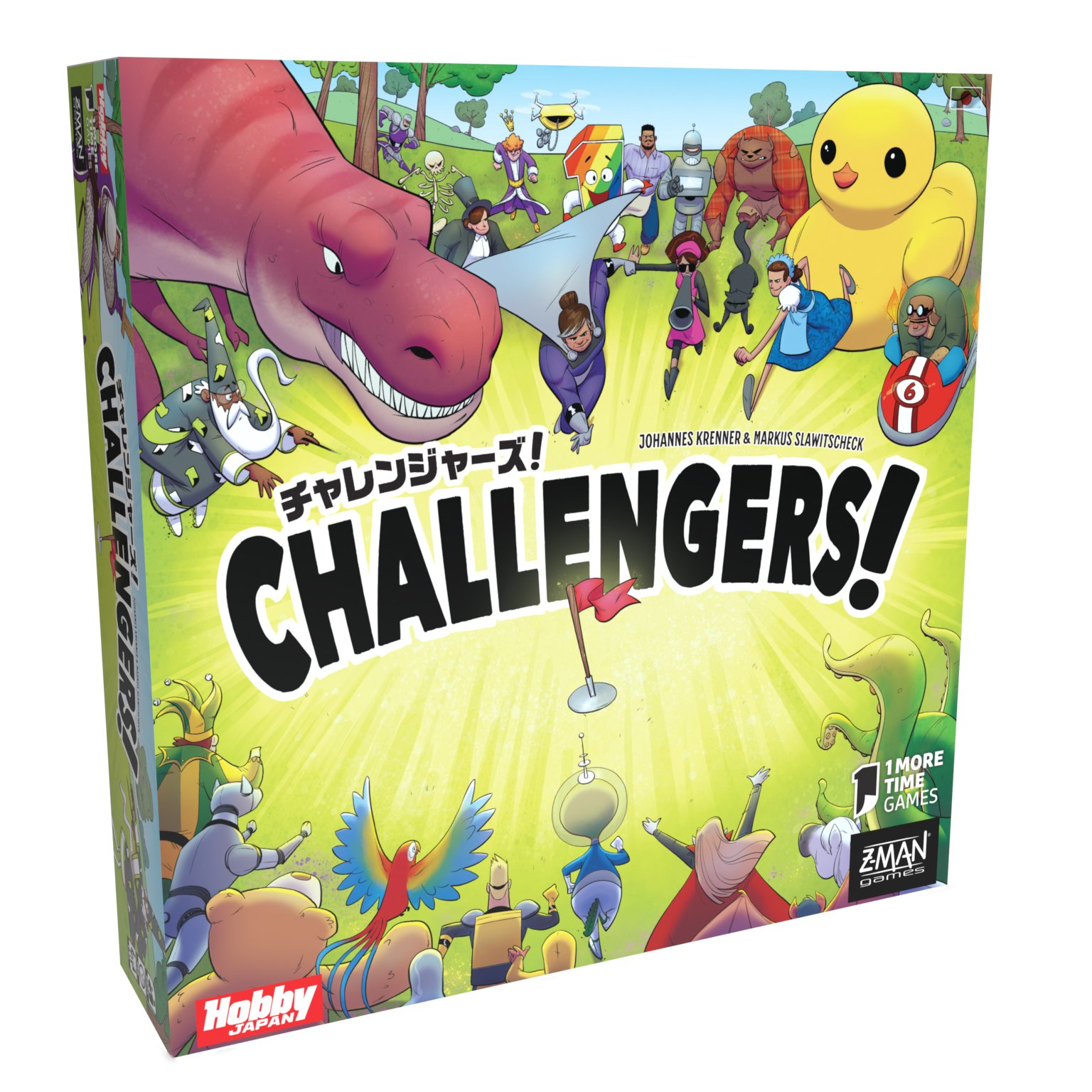■前置き
2023年から2024年の期間、ブログは一切書いていませんでしたが月1~2回程度はボードゲームで遊ぶ機会に恵まれており、新規タイトルもそれなりに遊びました。
今回は、その中で面白かったもの、印象的だったもの最高ベスト6をご紹介いたします。
(ベスト5のつもりで記事を書いていたら、途中で一作入れ忘れてるのに気づいてベスト6になってしまいました……。)
■選考基準(ボードゲームの評価項目)
・自分が2023年~2025年に初プレイした作品(=出版年は問わない)
・ゲームの重さ(プレイ時間)は問わない
・「ボードゲームの評価項目」というものそれだけで一記事書けそうなくらいなテーマですが、今回は下記のように定めます。自分の好みのゲームが高めの点数になるように調整された評価項目です。
評価基準は下記の5つとします。
①新規性:既存のゲームにはない目新しい要素があるか(10点満点)
②リプレイ性:2回以上プレイしたいと思えるか(10点満点)
③インタラクション:ソロプレイ感が少ないか、インタラクションが不快すぎないか(10点満点)
④爽快さ:プレイしていて気持ちよさを感じる瞬間があるか、プレイに「自分が上手くやってる感」があるか(5点満点)
⑤快適さ:アートワークのデザイン、コンポーネントが分かりやすいか、ルールに煩わしい処理が少ないか、ルールが複雑すぎないか(5点満点)
例えば、ユーロゲームの中で私が一番繰り返しプレイしているゲームを2025年基準で上記の項目に当てはめると…

タイトル:Agricola(アグリコラ)(旧版) 重さ:4/5
①新規性:6/10点
ワーカープレイスメントのクラシック的作品のため、今の視点での目新しさはない。
ただ、初めてプレイする現代プレーヤーは救済措置の少ないワーカープレイスメントは逆に新鮮に感じると思われる。
②リプレイ性:10/10点
文句なしのリプレイ性。豊富なユニークカードにより毎度一期一会のゲームが生成されるすごさ。
③インタラクション:10/10点
箱庭ゲームでありながら、各々のプレイ指針・出されるカードにより起こる資源価値の変動による緩やかなインタラクションやワーカープレイスメントによる直接的なインタラクション(資源カットやアクションカット、終盤の改築・柵の奪い合い)もあり。
スタンダードルールとして採用されるドラフトや、インタラクションを直接的に上乗せする職業カード(職業の枚数を競わせたり、ワーカーの数を競わせたり…)も存在。
④爽快さ:4/5点
瞬間的なものよりも、ゲーム終了時に思い通りプレイできた時の爽快さが強い。
プレイ中は基本的に嫌な思い(木が全然取れない…など)をしていることが多い。
⑤快適さ:3/5点
子供の食料の量や種まき、繁殖のルールなど覚えなくていけないルールはそれなりになるが量は少な目。
テキストによるユニークなカード効果によるコンボの処理など、ハウスルールによって解釈が分かれる処理が多い。
合計:33点/40点
■最高ベスト6の紹介
それではベスト6を紹介いたします。
良い点だけでなく、気になってしまう点も記載しているので全体的に辛めのコメントになってしまいましたが、間違いなく面白かった6作品です。
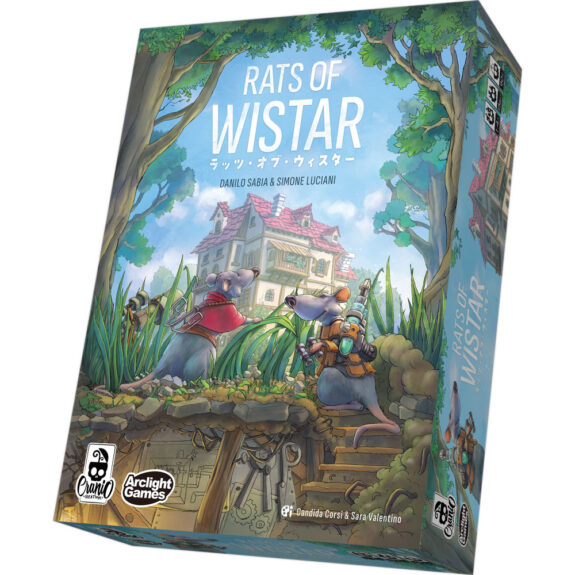
6位:RATS OF WISTER(ラッツ・オブ・ウィスター) 重さ:3/5

①新規性:6/10点
既存のメカニクスを組み合わせたゲームで、特段目新しさはない。
要素の多さの割に中量級のようにプレイ感が軽いのが特徴かもしれない。
②リプレイ性:7/10点
ユニークで豊富なカードによりリプレイ性は担保されている。しかし、アグリコラのように毎度別のゲーム展開がされることはなく、毎度似通ったプレイ感。
③インタラクション:6/10点
早取り、緩めのワーカープレイスメントといった現代ボードゲームの中でスタンダードなインタラクションの設定(=ソロゲー感は強め)。
④爽快さ:5/5点
わかりやすく拡大再生産(アクションポイント・パッシブ・定期収入・カードのタグ)、コンボゲーであるため爽快感がある1アクションが生まれやすい作り。爽快さ・気持ちよさをひたすら追求したようなゲーム。
⑤快適さ:3/5点
コンボが重なると処理が煩雑になってくるが、快適さを損ねるほどではない。
個人ボード下段に開放能力を小さなキューブで埋めるが、ダブルレイヤーになっておらずズレがち。
合計:27/40点
5位:CHALLENGERS!(チャレンジャーズ!) 重さ:2/5

①新規性:10/10点
大枠ではデッキビルディングの一種に分類されるが、類似の(アナログ)ボードゲームが思いつかないほどの新規性。ボードゲームも既存メカニクスをいかに組み合わせるか、というサンプリングの時代に突入してると思われるが、その中で異彩を放った作品。
そうとはいっても、ゼロベースからの発想ではなく、「バトルグラウンド」や「TFT」に代表されるデジタルゲームのオートチェスを参考にしたと思われるゲームデザインだが、そのエッセンスのアナログゲームへの落とし込み方があまりに完成されている。
ゲームシステムのデザインだけでなく、毎ラウンド違う対戦相手と総当たりで戦う「TCGのゲーム大会」を再現するという体験の新しさも素晴らしい。
②リプレイ性:8/10点
カードプールへの理解が深まるごとに上達するので、リプレイへの欲が出る。
1プレイ1プレイがライトで、ゲーム会で一日で複数回遊ぶことに対しての不満も出にくい。
ただ、対戦中のプレイヤーの判断はなく、プレイはほぼデッキビルディングのみのため引き運の要素が強くゲームへの一定の理解が深まると一気に熱が冷めやすい。
③インタラクション:6/10点
「1対1の総当たりの大会を行う」ので、全員で遊んでいる感覚が演出されるが、ゲーム性の部分でのインタラクションは薄い。
デッキ種類ごとの相性は無きにしも非ずだが、プレイングで調整することはできない。
④爽快さ:3/5点
コンボデッキが組めた時に気持ちよさはあるが、自らの判断の結果というよりも単に「引けるか・引けないか」に依るところが大きい。
思った通りにカードが引けず、いびつなデッキを抱えてゲームを終えることも多々ある。
⑤快適さ:3/5点
カードテキストによる効果の処理があるが、特に処理に戸惑うものはない。
合計:30/40点
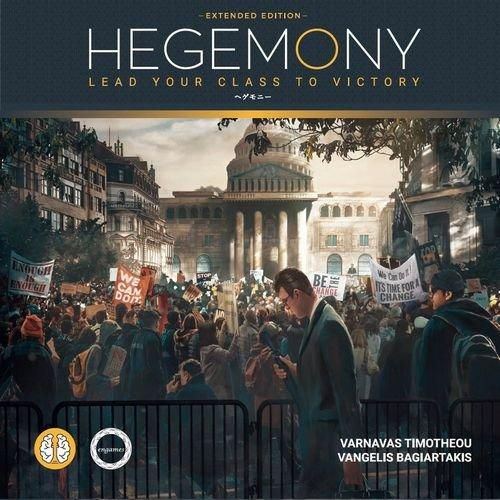
4位:HEGEMONY(ヘゲモニー) 重さ:5/5


①新規性:10/10点
ゲーム性よりも、現実世界の「労働者」「資本家」「政府」の経済的な関係性・連動性をボードゲームで再現度を優先したのかと思うようなゲームデザイン。
既に各所で言われている通り「経済シミュレーター」のような趣があり、ごっこ遊びの最上級のような体験ができる。それでいてゲームとして成り立たせる凄み。
ここまでフレーバーで評価(体験)を上げているボードゲームは他にないのでは。
②リプレイ性:8/10点
ルールが非対称なプレイアブルキャラクターとして「労働者」「資本家」「中産階級」「政府」の4つのクラス(役割)が用意されており、4回分のリプレイは担保されている。
それ以上のリプレイに関しては、実際にゲーム性が高い(プレイ中の判断が勝敗に左右されやすい)のは「中産階級」で他のクラスのプレイ感は毎度似たものになりがち。
「中産階級」をプレイできるのは当然1ゲームで一人なのがもどかしいところ。
③インタラクション:8/10点
各アクションが他プレイヤーに影響を及ぼすが、見かけほど直接的なインタラクションは感じない。
パッと見では全体のバランサーにように見える政府がその役割を担っておらず、めくられた目標カードに左右されるクラスになってしまっている。
「選挙」の全体に与える影響が大きいが、「労働者」と「資本家」はスタンスがほぼ固定なため、実質的な手綱は「中産階級」と「政府」が握っている。
また、ゲーム中「誰が勝っているか」が明確でないため、プレイヤー間の叩き合いでバランスが取りにくい作り。
④爽快さ:3/5点
クラスによって異なる。
「資本家」は一気にスコアが伸びる派手な動きがあり、爽快さを感じる場面もあるが、全体的に爽快感は少な目。
⑤快適さ:2/5点
ルールが非対称なゲームの宿命ではあるが、インストの負担が非常に大きい。
卓に参加するプレイヤー全員にそれなりの覚悟が必要なため、それを鑑みるとリリース直後の流行が終わった後に卓が立ちにくいタイプのゲームであると思われる。
合計:31/40点

ゲーム会に突如現れたサマリーロボ

3位:NUCLEUM(ニュークレウム) 重さ:4/5


①新規性:8/10点
「ブラス×バラージ」と評されることが多いが、個人的には「バラージ2」もしくは「バラージの鉄道フレーバーバージョン」といった感覚で、ブラスらしさや鉄道ゲームらしさは薄目。
バラージ好きの私にとってはすごくツボを刺激される作品。(逆に、身内のブラス好きには刺さっていない様子。)
全体的なプレイ感はバラージに近いが、アクションの選択方法やアクションタイルが線路になるなど目新しさもある。
②リプレイ性:9/10点
プレイヤーごとに4種類の固有能力(固有の個人ボード)があり、ヘゲモニーほどではないがリプレイ回数は担保されている。
建物や線路を展開するマップ上の位置に強弱があり、定石がある作りになっているが、定石を発見するまでは非常に楽しめる。
定石発見後ももちろんゲームは成立するが、煮詰まるとバラージのようにゲーム開始時に手番を点数でオークションする必要が出てくるかもしれない。
③インタラクション:8/10点
早取りや線路の絡みなど、インタラクションはあるが不快感が少ない現代的な有り方。
直接的にインタラクションが発生するアクションでは「叩き」ではなく「Win-Win」であることが多い。
④爽快さ:4/5点
徐々に個人能力が解放されて行き、強い動きができるようになっていく。
線路の色一致によるアクション(上手くやってる感)や、リチャージなど随所に気持ちがいい動きがちりばめられている。
後半は報酬獲得→即達成の動きが多くなり、気持ちよさがある。
⑤快適さ:3/5点
ルール量は多めで、「発電のルール」や「ネットワークの概念」など理解しにくい部分もいくらかあるが、一般的な重ゲーの範疇。
合計:32/40点

写真右上の紫の地域がとても強い

2位:FEDERATION(フェデレーション) 重さ:3/5


①新規性:9/10点
コマを表と裏のどちらで置くか選択するワーカープレイスメント。
1回のワーカー設置がアクション選択かつ2種類のマジョリティ争いの投票にもなっている(=1アクションで三重の意味を持つ)というジレンマが効いた非常にユニークなシステム。
②リプレイ性:8/10点
展開の仕方や各アクションごとの強弱などプレイを重ねるごとに見えてくるので、リプレイ意欲が刺激される。
ただ、展開に幅は出ないので10回以上のリプレイに堪えうるかというとそれは難しい。(拡張は未プレイ)
③インタラクション:9/10点
同じアクションスペースが複数ある(=事故が起きにくく不快感が少ない)現代的なワーカープレイスメントではあるものの、二重のマジョリティ争いによりインタラクションの強め。
④爽快さ:4/5点
基本的には何をやってもプラスに働くアッパーな作りで、ゲームが進むにつれて定期収入が増えたりやアクションが強くなっていく。
投票により大きく得点が入るケースもあり、爽快感があると言える。
⑤快適さ:4/5点
ルールはシンプルにまとめられており、(アタルムのタイルのアイコンにわかりにくいものがないとは言えないが)わかりにくい処理も少ないと感じる。
個人的にボードのデザインや色見、コンポーネント(特にワーカー駒)にフェティッシュを感じる。
合計:34/40点

BGAでも遊べます
/picture_6c8ef859-ca91-462f-9f33-77dccbcfe108.webp)
1位:Sankoré(サンコーレ) 重さ:4/5
①新規性:10/10点
ロピアーノ作品に触れるのが初めてだったことも影響していると思うが、新鮮さを強く感じた。
「何をやっても得点になる」ポイントサラダのゲームが増える中、最終的な図書館マジョリティ争いで集めた得点源が0点になる可能性があるのも逆に新しい。
個人ボードのアクションスペースと共通ボードの4つアクションエリア、3種類の資源、図書館マジョリティなど各要素が緻密に絡み合い、プレイ中はその中でベストな鋭い一手を模索するボードゲームの根源的な楽しさが溢れていると言える。
②リプレイ性:9/10点
過去3回プレイしたが、その中ではまだ定石の発見には至らず毎度異なる展開が楽しめている。
ただ、アクションごとパワーが歪んでおりマジョリティでのインタラクションによるバランス調整機能を凌駕する強い定石はあると思われる。(具体的には、天文学が弱く、数学が強い。)
影響力はそこまで大きくないが、毎度配れる個人目標(個人能力)も嬉しい。
③インタラクション:9/10点
インタラクションは、早取りと各種マジョリティ争い。
特に図書館のマジョリティは最終的な勝敗に直結しするのでプレイ全体を包括する大きなインタラクション要素。プレイヤーにバランス調整を委託作りしているので、モンバサの最終盤のようにキングメーカーが発生しうるが、今のところ問題になるような動きは出ていない。
この図書館のマジョリティの動きに応じてプレイを調節する必要があるのも楽しい。
④爽快さ:4/5点
アクションポイントやエンジンビルドなど、後半の方が強い動きができる作りで尻上がりに強いアクションを打てるような設計。
⑤快適さ:3/5点
ルール量は多くないものの直感的ではなく、初見時は全体像の見通しが立たないため何をすべきか迷子になりやすい。
サポートアクションのルールなど細かい部分で注意が必要な点もある。
各種資源の配置のランダマイザ―として袋引きを多用するセットアップはやや煩雑。
良い点として、ゲーム中は一切得点が入らない作りなのは快適で、ロピアーノのゲーム特有のボード・コンポーネントの配色好み。
合計:35/40点
毎ゲームランダムに配られる固有能力付の目標カードは強力すぎず、オーディンの祝祭の職業カード程度の可変要素
■おわりに
今回は、「新規性」「リプレイ性」「インタラクション」「爽快さ」「快適さ」の5つの評価項目に、重みを付けて調整した状態で点数付けを行いました。
自分の好みのゲームが上位になるような評価項目を選定しましたが、項目が変わればこのランキングも変動します。
例えば、ヘゲモニーは今回4位でしたがプレイ体験としては一番印象に残っている(=評価項目によっては1位になりうる)、と言ってもいいかもしれません。
また、個人的に(アグリコラのような)鉄のリプレイ性を持ったゲームの出現を願っているのですが、出版社側の経済的な事情(1つのゲームだけ繰り返されるとゲームが売れない)や現状のプレイヤー側のスタンス(同じゲームを複数回遊ばないのがスタンダード)を考えると、現代ではボードゲーマーが5回遊べうるゲームは、十分リプレイ性があると言っていいのかもしれません(プレイヤー側もそれ以上のリプレイを望んでいない)。
今回の6作が、皆様のボードゲーム選びの参考になれば幸いです。